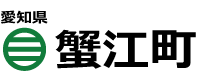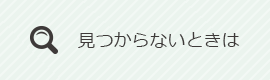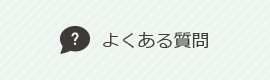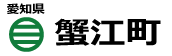本文
後期高齢者医療
◆後期高齢者医療
-
後期高齢者医療制度は、愛知県内のすべての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」が制度を運営します。町で行う業務は、保険料の徴収、申請や届出の受付、資格確認書の引き渡しなどです。
◆対象者 (被保険者)
- 町内に住所を有する75歳以上のかた。
- 町内に住所を有する65歳以上の一定の障害をお持ちのかたで、広域連合が認めたかた。
◆資格確認書の交付
令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方
- 資格確認書を自動的にお誕生日までに簡易書留郵便で送付します。
- 65歳の一定の障害をお持ちのかたは、窓口にて交付申請してください。
※75歳の誕生日から「マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証」を医療機関で提示して受診してください。
令和7年8月1日以降に75歳のお誕生日を迎える方
- マイナ保険証を保有している方
「資格情報のお知らせ」をお誕生日までに送付します。 - マイナ保険証を保有していない方
「資格確認書」をお誕生日までに簡易書留郵便で送付します。
※マイナ保険証のつきましては、下記のページもご覧ください。
令和6年12月2日からマイナ保険証による受診を基本とする仕組みへ移行します
◆医療機関窓口での一部負担金の割合
医療機関にかかったときの医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。
※一部負担金の割合が3割と判定された方でも、以下の(1)~(4)の場合は2割または1割負担となります。
(1) 被保険者の方が1人の世帯の場合・・・被保険者の前年中の収入額が383万円未満のとき
(2) 被保険者の方が1人で、その被保険者の前年中の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯の場合・・・被保険者と70歳から74歳の方の前年中の収入額の合計が520万円未満のとき
(3) 被保険者の方が2人以上いる世帯の場合・・・被保険者の前年中の収入額の合計が520万円未満のとき
(4) 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者の前年中の旧ただし書所得(所得金額から基礎控除43万円(基礎控除43万円は所得2,400万円超となるとその所得に応じて減額されたり、適用が受けられなくなります。)を控除した額)の合計が210万円以下の世帯
後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります [PDFファイル/511KB]
愛知県後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト<外部リンク>
厚生労働省(後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について))<外部リンク>
◆保険料
後期高齢者医療は、75歳以上のかた、被保険者となった65歳以上の一定の障害をお持ちのかたに納めて頂く保険料と国・県・町の公費及び若年者からの支援金を財源に運営します。
保険料の額は、全員のかたに「等しく負担して頂く均等割額」とそれぞれのかたの「所得に応じて負担していただく所得割額」との合計額になります。
<令和4・5年度保険料の計算方法>
所得割額(所得金額-※43万円)×所得割率9.57%+被保険者均等割額 49,398円=保険料額(限度額66万円)
<令和6・7年度保険料の計算方法>
所得割額(所得金額-※43万円)×所得割率11.13%(所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の被保険者の令和6年度の所得割率については10.40%を適用し所得割額を算定する。)+被保険者均等割額 53,438円=保険料額(限度額80万円)
賦課限度額については、令和6年度に新たに75歳に到達するかたを除き73万円となります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
→詳細は「愛知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください<外部リンク>
◆納めかた
特別徴収
要件
- 年金額が年額18万円以上の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えない方
※要件を満たす方でも受給している年金の種類により、年金からの支払いにならない場合があります。
※「特別徴収中止の申請」により、年金からの支払いに替えて「口座振替」を選択された方は該当しません。
納付方法
年金の定期払い(年6回偶数月)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
要件
- 特別徴収の要件に該当しなかった方
- 年度途中で被保険者となる方
納付方法
町から送付される納付書で、保険料を個別に納めます。
金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付することもできますが、窓口まで出かけることなく納付することも可能です。
納付方法は主に下記のとおりです。
- 蟹江町役場
- 銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫
- コンビニエンスストア
- 口座振替(郵便局、銀行もしくは役場にてお手続きが必要です。)
- スマートフォン決済サービス(Pay Pay・LINEPay・PayB・auPAY・FamiPay)
◆代理のかたがお手続きをされる場合について
被保険者本人が入院や施設入所等で来庁できない場合など、代理のかたがお手続きをする場合は、委任状が必要となります。委任状 [PDFファイル/152KB]
また、後期高齢者医療に関する通知(保険料決定通知等)の送付先を変更することができます。なお、後期高齢者医療以外の送付先の変更を希望される場合は、別途お手続きが必要です。送付先変更申請書 [PDFファイル/147KB]