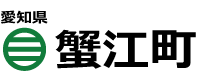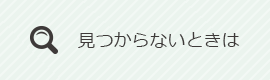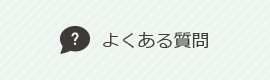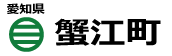本文
平成19年度以降の町県民税の主な改正点
<平成19年度から実施される主な改正>
1 平成19年度分から、住民税所得割の税率が一律10%に統一されます。
| 改正前 | 改正後 | |||
|---|---|---|---|---|
課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 | |
個人住民税 | ~200万円 | 5% | 一律 | 10% |
200~700万円 | 10% | |||
| 700万円超 | 13% | |||
うち | ~700万円 | 2% | 一律 | 4% |
700万円超 | 3% | |||
うち | ~200万円 | 3% | 一律 | 6% |
200~700万円 | 8% | |||
700万円超 | 10% | |||
所得税と個人住民税の税率
所得税と個人住民税の合算税率(所得税については平成19年分以後から、個人住民税については平成19年度分以後適用)
税源移譲によって住民税が増えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。
改正後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課税所得 | 税率 | 課税所得 | 税率 | ||||
| 所得税 | 住民税 | 合計 | 所得税 | 住民税 | 合計 | ||
| 200万円以下 | 10% | 5% | 15% | 195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
| 330万円以下 | 10% | 10% | 20% | 330万円以下 | 10% | 10% | 20% |
| 700万円以下 | 20% | 10% | 30% | 695万円以下 | 20% | 10% | 30% |
| 900万円以下 | 20% | 13% | 33% | 900万円以下 | 23% | 10% | 33% |
| 1800万円以下 | 30% | 13% | 43% | 1800万円以下 | 33% | 10% | 43% |
| 1800万円超 | 37% | 13% | 50% | 1800万円超 | 40% | 10% | 50% |
2 調整控除の創設(住民税と所得税の人的控除差について)
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は所得税よりも多くなり、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまします。このため、個々の納税者の人的控除に適用状況に応じて、住民税を減額することにより、納税者の税負担が変わらないようにしています。| 所得税 | 住民税 | 控除の差 | |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 扶養控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定扶養控除 | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
3 定率減税の廃止
・平成19年度分の個人住民税より廃止となります。
ただし、所得税については、平成18年分については2分の1、平成19年分から廃止となります。
<平成20年度から実施される主な改正>
損害保険料控除制度を改組し、地震保険料控除が新たに創設されました。
現行の損害保険料控除は平成18年末で廃止し、新たに地震保険料だけを対象とする保険料控除制度が創設されました。
- 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とした地震保険契約。
- 地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金または共済金が支払われる地震保険契約。
※平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、現行の長期損害保険料控除(最高1万円まで)の適用ができます。ただし、地震保険料控除と併用する場合は、合わせて2万5千円が上限となります。(所得税は保険料等の全額で最高5万円まで)
<平成21年度から実施される主な改正>
公的年金からの特別徴収が始まります。
1.制度の内容
公的年金等に対する町民税・県民税は、これまで、年4回に分けて金融機関等の窓口で納付していただいておりました(普通徴収といいます)が、地方税法の改正により平成21年10月からは、年6回の公的年金支給のつど、公的年金から差し引いて納税する制度(特別徴収といいます)が開始します。
2.特別徴収の対象となるかた
65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の方で、町民税・県民税の納税義務のある方が対象になります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、これまでどおりの普通徴収となります。
- 1月1日以降に町外に転出された方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 特別徴収される年金の年間給付額が18万円未満の方
- 特別徴収される税額が年金から引ききれない方
3.特別徴収の時期と税額
公的年金からの特別徴収が始まる年度
10月から、公的年金支給のつど(10月、12月、2月)、年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納付(特別徴収)していただきます。
年度の前半(6月、8月)については、年税額の1/4の額を、納税通知書または納付書によって納付(普通徴収)していただきます。
特別徴収開始後の年度
4月、6月、8月は、前年度の2月と同じ額を、公的年金から差し引いて納付していただきます(仮特別徴収)。 10月、12月、2月は、年税額から4月、6月、8月に仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3を、公的年金から差し引いて納付していただきます。
寄付金控除の改正
寄附を行った際の控除方式が所得控除から税額控除へ改正されるとともに、控除の対象となる金額が拡大されます。また、地方公共団体に対する寄附金については、その寄附金額のうち下限額を超える金額について所得税とあわせて一定の限度額までは、全額が控除できるようになりました。
(寄附金控除) | 改正後 (寄附金税額控除) | |
控除方式 | 所得控除 | 税額控除 |
控除対象となる寄附金の上限額 | 総所得金額の25% | 総所得金額の30% |
控除対象となる寄附金の下限額 | 10万円 | 5千円 |
<平成22年度から実施される主な改正>
新しい住宅ローン特別控除の創設
1.制度の内容平成21年から平成25年までに新築または増改築の住宅に入居した方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別 控除額がある場合に、個人町民税・県民税から控除する住宅ローン特別控除が創設されました。
また、現在、平成11年から平成18年までに入居した方に適用されている「住宅ローン特別控除申告書に基づく住宅ローン特別控除」についても同様の仕組みとされ、給与支払報告書(個人別明細書)や確定申告書に住宅ローン特別控除に関する事項が記載されることにより適用を受けられますので、従業員の方が住宅ローン特別控除申告書を市町村へ提出することは不要となりました。
上場株式等に係る配当所得の申告分離課税の創設
平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択できるようになりました。(同一年中に申告する上場株式等に係る金額の合計額についての選択になります。一部について選択することはできません。) 制度の概要は以下のとおりです。税率 | ||
| 町民税 | 県民税 |
申告分離課税 | 1.8% | 1.2% |
総合課税 | 6% | 4% |
- 申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はありません。
- 申告分離課税を選択した場合も、合計所得金額(扶養控除や非課税の判定に使用します)の算出に含まれます。
- 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能です。
<平成23年度から実施される主な改正>
寄附金税制の見直し(住民税は平成24年度から)
町・県民税の寄附金税制が拡充され、次の点が変わりました。
(1).寄附金控除の適用下限額の引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円へ引き下げ。
(2).町・県民税の控除対象寄附金の拡大
寄附金税額控除の適用対象に、認定NPO以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県が条例において指定した適用対象寄附金に係る控除額については県民税から、町が条例において指定した適用対象寄附金に係る控除額については町民税からそれぞれ控除されることとなります。
年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告が不要となります。
※住民税の申告手続きは必要ですのでご注意ください。
上場株式等の譲渡及び配当の課税について(平成25年12月31日まで)
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、町・県民税3%)が2年延長となります。平成26年1月から20%となります。
<平成24年度から実施される主な改正>
扶養控除等の見直し
1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の方をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
2.特定扶養親族の範囲の変更
年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、これらの方に対する扶養控除の額が33万円となりました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
3.同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置について、特別障害者に対する障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められました。
寄付金税額控除の見直し
寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。
退職所得の分離課税について
勤続年数5年以下の役員等(※)に支払われる退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする措置が廃止されました。
(※)勤続年数5年以下の役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方をいいます。
これらの改正は、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。
<平成25年度から実施される主な改正>
生命保険料控除の見直し
介護医療保険料控除が創設されたことに伴い、生命保険料控除が改組され、次の1から3までの各保険料控除の合計額とされました(合計適用限度額は7万円です。)
1 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)
新契約に係る控除について、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は28,000円とされました。控除額の計算方法は下記をご覧ください。
| 平成23年12月31日までに締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。) | |
支払保険料等の金額 | 控除額 |
12,000円まで | 支払保険料等の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,001円から | 28,000円 |
2 平成23年12月31日までに締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)
旧契約に係る控除については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額は35,000円です。)が適用されます。控除額の計算方法に変更はありません。
| 新契約と旧契約の両方についての控除の適用を受ける場合の控除額の計算 | |
支払保険料等の金額 | 控除額 |
15,000円まで | 支払保険料等の全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,001円から | 35,000円 |
3 新契約と旧契約の両方についての控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の両方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれの契約に応じて計算した金額の合計額(適用限度額は28,000円です。)とされました。
平成26年1月から、記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)を制度の対象とすることとされました。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
<平成26年度から実施される主な改正>
給与所得控除の見直し
その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、245 万円の定額とすることとされました。
町民税・県民税の均等割額の引き上げ及び「あいち森と緑づくり税」の延長
地方公共団体が実施する東日本大震災の教訓をふまえた防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間、町民税と県民税の均等割額について、それぞれ500円を引き上げた額とすることとされました。
なお、愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により県民税の均等割額は1,500円とされていましたが、その適用期限を平成30年度まで延長することとされました。
寄附金税額控除の特例控除額の見直し
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から平成50年度までの寄附金税額控除の特例控除額の算出に用いる所得税の税率について、復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算することとされました。
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)について、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後に支払を受ける配当及び譲渡所得等から、本則税率(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
<平成27年度から実施される主な改正>
住宅ローン控除の延長・拡充
住宅ローン控除について、対象期間が平成31年6月まで延長されるとともに、平成26年4月以降に入居した方については、控除限度額が引き上げられることとされました。
入居した年月 | 控除限度額 |
平成25年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年1月から | 所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月から | 所得税の課税総所得金額等の7% |
(注) 平成26年4月以降に入居した方でも、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%でない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る町民税・県民税について、軽減税率(町民税:1.8%、県民税:1.2%)が廃止されました。これに伴い、平成27年度から本則税率(町民税:3%、県民税:2%)が適用されることとなりました。
町民税と県民税の税率は以下の表のとおりです。
区分 | 平成27年度以後 | 平成26年度 |
申告分離課税を選択した上場株式等の 課税配当所得の金額 | 町民税:3% 県民税:2% | 町民税:1.8% 県民税:1.2% |
上場株式等の課税譲渡所得等の金額 | 町民税:3% 県民税:2% | 町民税:1.8% 県民税:1.2% |
<平成28年度から実施される主な改正>
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除について、対象期間が平成31年6月30日まで延長されることとされました。ふるさと寄附金(納税)に係る寄附金税額控除の見直しと「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
1.ふるさと寄附金(納税)の拡充
都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(納税))を支払った場合における特例控除額の上限額について、所得割額(税額控除前)の10%から20%に引き上げられることとされました。
特例控除額の上限額 | |
平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附金を支払った場合) | 所得割額(税額控除前)の10% |
平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附金を支払った場合) | 所得割額(税額控除前)の20% |
2.特例控除額の算出方法の見直し
所得税の最高税率が引き上げられたことに伴い、特例控除額の算出に用いる割合について変更されることとなりました。
特例控除額=(都道府県・市区町村への寄附金-2,000円)×(下表の割合)
| 特例控除額の算出に用いる割合 | |
課税総所得金額―人的控除差の合計 | 割合 |
0円未満 | 90% |
195万円以下 | 84.895% |
195万円を超え330万円以下 | 79.79% |
330万円を超え695万円以下 | 69.58% |
695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
900万円を超え1800万円以下 | 56.307% |
1800万円を超え4000万円以下 | 49.16% |
4000万円超 | 44.055% |
3.「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
確定申告が不要な給与所得者等の方が、平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(納税))を支払う際に、寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告をしなくても町民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
※「申告特例申請書」に記載した住所や氏名等に変更があった場合は、寄附金を支払った年の翌年の1月10日までに寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができない場合
「申告特例申請書」を提出していても、次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。なお、その際は市区町村からお知らせ(通知)が送付されます。
- 所得税の確定申告書を提出した場合
- 町民税・県民税申告書を提出した場合
- 寄附先の都道府県・市区町村が6団体以上の場合
- 「申告特例申請書」または「申告特例申請事項変更届出書」に記載した市区町村と、寄附金を支払った年の翌年の1月1日(賦課期日)に住所がある市区町村が異なる場合
お知らせ(通知)が送付された場合、「申告特例申請書」を提出した寄附金について寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書または町民税・県民税申告書を提出する必要があります。ただし、すでに提出した所得税の確定申告書または町民税・県民税申告書で、「申告特例申請書」を提出した寄附金について申告している場合は不要です。
医療費控除などを受けるために、所得税の確定申告書または町民税・県民税申告書を提出する場合は、「申告特例申請書」を提出した寄附金についてもあわせて申告してください。
平成27年1月1日から3月31日までに支払ったふるさと寄附金(納税)について
この期間に支払った寄附金については、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができませんので、寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書または町民税・県民税申告書を提出する必要があります。また、平成27年4月1日以後に支払った寄附金についてもあわせて申告してください。
申告特例控除額について
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、申告特例控除額として、所得税および復興特別所得税における控除分に相当する額が寄附金税額控除額とあわせて町民税・県民税から控除されます。